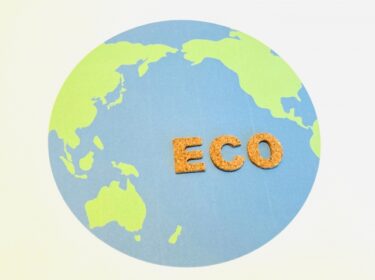再エネを地域でつかい、地域で育てる――営農型太陽光発電による新しい共生モデルを探る
再生可能エネルギーと地域社会のこれから
脱炭素社会の実現に向けて、全国の自治体や企業が再生可能エネルギーの導入を加速させる中、「地域でつくった電気を、地域で使う」という“地産地消型”のエネルギーモデルが注目を集めています。特に、広い土地を持つ農業地域では、農業と発電を両立させる「営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)」が、持続可能な地域電力の一翼を担う仕組みとして期待されています。
ソーラーシェアリングとは何か
営農型太陽光発電は、農地の上部に太陽光パネルを設置し、その下で農作物の生育を続ける手法です。この方式は、単なる発電設備の導入にとどまらず、「農業をしながら電気もつくる」という新たな土地活用の可能性を提示しています。農地の機能を損なわずに、同時に地域の再エネ供給源となる――まさに“農業と発電所”の共生といえるでしょう。
地域電力会社との連携が鍵
近年、地域密着型の電力会社(いわゆる“新電力”)が、自治体や地元企業と連携し、地域内で発電された電気の地産地消を進めています。営農型太陽光で得られた電力を、地域の学校や福祉施設、農業用のポンプ・冷蔵施設などに供給することで、地域全体のエネルギー自給率を高めることが可能になります。こうした取り組みは、電力料金の地域内循環にもつながり、エネルギーの地産地消と経済的な地域貢献を両立させます。
地域の理解と協働の重要性
営農型太陽光発電の普及には、農業者だけでなく、自治体や電力会社、地元住民との協力が不可欠です。特に農地転用許可や系統連系など、制度面での手続きが多いため、計画段階から関係者の合意形成を丁寧に進めることが求められます。また、地域住民の「風景が変わる」ことへの不安に対しても、丁寧な説明や現地見学などを通じて、共感と納得を得る姿勢が大切です。
災害時の地域インフラとしての役割
営農型太陽光発電のもう一つの大きな利点は、災害時のレジリエンス強化にあります。分散型の電源として、停電時に地域の非常用電源として活用できるほか、蓄電池と組み合わせれば、通信・照明などの最低限の生活機能を維持する拠点にもなり得ます。農業と発電の共生は、エネルギー面だけでなく、防災面でも地域の安心を支える基盤となるのです。
まとめ
地域に根ざした営農と再生可能エネルギーの融合は、単なる電力確保にとどまらず、地域社会の持続可能性そのものを高める可能性を秘めています。農地を活かしながらエネルギーを創出し、それを地域の暮らしや産業に還元していく仕組みづくり――それが「共生によるエネルギー自立」の本質です。今こそ、地域の知恵と力を結集し、農業と電力の未来をともにつくっていく時です。